HOME > マコメ研究所のセンサー技術 > ゼロからはじめる磁気応用技術(その2)
ゼロからはじめる磁気応用技術(その2)

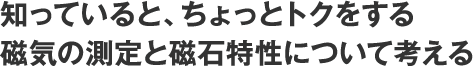
様々な種類の磁気測定器の違いと
磁気測定にまつわる“本当とウソ”
第1回に続き、磁気の測定と永久磁石の特性について簡単な例を上げて説明します。磁石の強さを測定する際、磁気測定器が必要となります。
代表的な磁気測定器には、「ガウスメーター」「テスラメーター」「フラックスメーター」などがありますが、それぞれ単位が異なるだけで基本的な関連があります。以前は磁束密度の単位として「G(ガウス)」が一般に使われていましたが、わが国も単位系が国際単位に統一されたために、「T(テスラ)」という単位を使うようになりました。
| 単位量 | 国際単位系 (mks単位系) |
従来の単位 (cgs単位系) |
|---|---|---|
| 磁 束 | Wb(ウェーバー) | Mx(マクスウェル) |
| 磁束密度 | T(テスラ) | G(ガウス) |
表 1Wb=1V・S、1Wb=1081Mx、1T=1Wb/m2、1T=104G
(磁束計=フラックスメーター)
磁束の単位「1Wb」とは、磁束を1秒間一定割合で下げ、0(ゼロ)にしたとき、それに鎖交する一巻きのコイルに誘起する起電力が1ボルトを生ずる磁束と定義されています。よって、「1T」とは1Wbの磁束が1m2の面積に対して垂直に流れているときの「磁束密度」となります。
最近、携帯電話やパソコン、送電線から漏れ出る電磁波を測定する「ガウスメーター」と呼ばれている磁気測定機器がありますが、我々が磁束密度計といっている機器と根本的に異なります。電磁波は交流電磁界ですから永久磁石のような静止磁界とは検出原理が異なるからです。磁気測定機器を購入する際には混同しないように注意が必要です。
一般に永久磁石の強弱を表すとき、実際の磁石表面の磁束密度や表面磁束密度を測定します。ただし、第1回でも説明しましたが、磁石の測定する場所や測定機器メーカーの違いにより値は微妙に異なります。また磁石形状が異なる物を測定しますと、同じ材料でも値は違います。そのため、磁石の強弱の目安にはなりますが、真の値とはなりません。実際に使用する用途に合わせて、同一条件と同一測定器で測定した相対値を比較するのが、現実的な磁石の磁気測定となります。
磁石の “強い、弱い” を決める
「残留磁束密度」と「保磁力」とは
製品カタログなどに記載されている永久磁石の特性に、「残留磁束密度」と「保磁力」という用語が頻繁に出てきます。
残留磁束密度は、磁石を飽和まで磁化させた後に、その外部磁界を減少させ、0(ゼロ)にしたとき、その磁石に残留する磁束密度のことです。また、保磁力はその残留した磁束密度が0(ゼロ)になるように反対方向に与えた磁界の強さのことをいいます。
これらの測定には、専用の磁気測定機器が使われ、磁石の性能比較を行う上で評価される値となります。図1は、その測定機器で測定した特性曲線でB-H曲線などと呼びます。ただし、磁石が残留磁束密度の値まで磁束密度が出ているという意味ではなく、あくまでも測定機器上の値です。そのため、磁石単体では残留磁束密度の数十分の一程度しか表面磁束密度が出ていませんので注意してください。
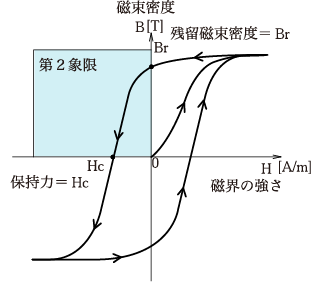
図1 B-H曲線(ヒステリシスループ)
一般に磁石の特性は、図1の第2象限の部分を取り出して減磁特性とか単に磁気特性などと表示されています。
この特性によって、磁石の設計や磁気回路設計の資料となります。図1のB-H曲線の軌跡上の点、B(縦軸値)×H(横軸値)の両者の積を求め、その最大値を最大エネルギー積といい、磁石の良し悪しの目安ともなります。単純に「残留磁束密度(Br)が高ければ強い磁石である」「保磁力(Hc)が高ければ安定した磁石である」といえ、最大エネルギー積が高いほど両者を兼ね備えた磁石といえます。
さて、カタログの残留磁束密度値が高ければ何となく強い磁石であると推察できますが、保持力の値が高いと何に影響するかというとことになります。
環境変化や形状サイズなどの条件下で
安定した磁力を確保するための目安
私たちの身の回りには色々な物に磁石が使われていて、その用途により様々な材料の磁石が使われています。高温、低温といった温度変化や磁石同士の接触、外部磁界中の設置など様々な使われ方をします。そこで問題なのが安定性です。せっかく高い磁束密度の発生する磁石でも内部、外部要因により、磁力が知らぬ間に下がったり、単に時間と共に磁力が下がってしまったのでは不安定で本来の性能が出せなくなります。
さらに厄介なのが磁石形状により特性が変化し、特に磁石を薄い板状に加工して使う場合、自己減磁作用という自ら磁力を落とす作用があります。これは、磁石から出ている磁束が外部に向けてN極から出てS極に戻りますが、わざわざ外部に出て戻るより、磁石内部を直接N極からS極へ流れた方が近道です。ところが、その各々の磁束の流れる向きが磁石内部で反対向きに流れてしまいます。
よって、図2のように、磁石内部では本来持っている磁束φaとすると、反対方向に流れる自己減磁作用による減磁束φbとの差し引きが外部に出てくる磁束φとなります。
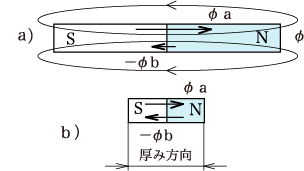
図2 自己減磁作用
また、この自己減磁作用は磁石の厚みが薄くなるほど接近するため強く自己減磁し、図2のb)のようにφaとφbがほぼ同じになってしまうと、外部磁束φは殆ど現れなくなります。
図3のような厚み2の円柱磁石を半分にすると、厚み1の磁石の磁束密度は元の半分にならず、それ以下となってしまいます。
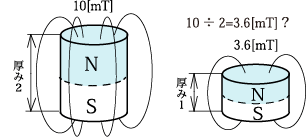
図3 磁石の厚みと磁束密度の関係
そのため、厚みの薄い磁石板は磁石にとって過酷な条件であると言えます。したがって、どのような磁石でも磁力を保ちながら薄い板状の磁石ができるとは限りません。そこで、磁石の保磁力が高いということは医学でいうところの病気に対抗する「免疫力」に相当し、内の癌や外の病原体と戦い健康状態を維持するような「復元力」の強さを現します。よって磁石の様々な取り扱いや環境の変化、形状が薄いなどの条件下で安定した磁力を確保するためには、保磁力の高い磁石材料を使うのが最良の選択となります。